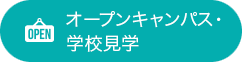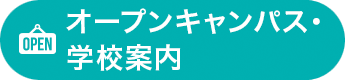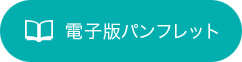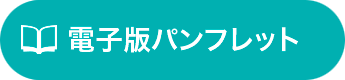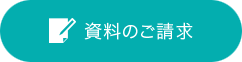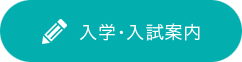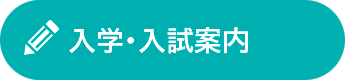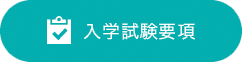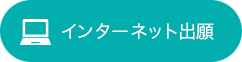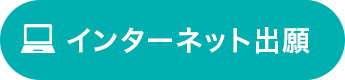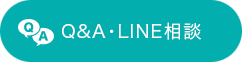【教職員インタビューVol. 10】ライフケア学科 柔道整復専攻 甲斐 範光先生にインタビューしました!
こちらのページでは、教職員がていたんの魅力などをご紹介しています✨
InstagramやXにも学生の日常の様子を掲載しています♪ぜひフォローしてください!
今回は、ライフケア学科 柔道整復専攻 甲斐 範光 先生にインタビューをしました♪

![]()
Q:甲斐先生は柔道整復師として実際の治療に従事されながら、30年以上教員として柔道整復師の養成に携わってきました。柔道整復師を志した理由を教えてください。
A:父親が柔道整復師でその後姿を見て育ちましたので、柔道整復師に憧れてこの業界に入りました。
Q:柔道整復師として治療の際に心掛けていることはありますか。
A:患者さんがケガをする前の状態と同じように「社会復帰ができることを目指す」、もしそれが叶わないのであれば「なるべくその状態に近い状態に近づける」ということを目標に治療しています。そのためには患者さんとの信頼関係が大事だと考えています。どのような治療であっても患者さんと治療する側の気持ちが通じていないと治療効果が半減すると考えていて、信頼関係が構築されてからようやく治療開始、というくらいの気持ちでいます。ケガをしたことで患者さんが不自由に感じているのはどのようなところなのか、何を解決したいのか、という患者さんのwantsをなるべく早く察して、そこにアプローチしてあげることを考えています。その意味で患者さんとのコミュニケーションをとても大切にしています。
Q:教員として、教育に当たる際の目標や気を付けていることなどありますか。
A:本専攻は柔道整復師の養成校ですので、柔道整復師の資格を取って社会に貢献できる人を育てたいと思っています。ただ資格を取れれば良いわけではなく、卒業後現場に出た際に実際に治療ができる医療従事者を育てたい。要は実学です。「治せる柔道整復師」を育てたいと思っています。学生には、「私を含めて教員から教わったことをそれが本当に正しいのかどうか、常に自分の頭で考えてから頭に入れるようにしなさい」と毎年言っています。教員が10人いれば10人ともちょっとずつ違うことを言うかもしれない。それを自分のものにする前に、本当にこれで大丈夫なのか、これで患者が治るのかを考えるように伝えています。
Q:先生が考える「柔道整復師の魅力」は何ですか。
A:柔道整復師の仕事を通して社会に貢献したいという自分の想いと、その想いを成し遂げる過程で、患者さんの喜びと自分たちの喜びとが一緒になってお互い正比例して大きくなっていく点でしょうか。患者さんと同じ目標に向かって同じベクトルで動いて行くなかで患者さんの喜びを自分の喜びとして感じることができる、そして患者さんと一緒になって喜んでいける、という点です。柔道整復師の仕事はそのような喜びを得ることのできる仕事の一つだと思っています。
Q:最後に、入学を考えている高校生の方へのメッセージをお願いします。
A:いろいろな仕事があるわけですが、入学後の勉強を考えると柔道整復師という仕事の明確なビジョンが描けるようになって受験した方がいいかと思います。柔道整復師は、医療専門職でケガを治す方法を突き詰めて考えていかなくてはいけない職種なのでやっぱり勉強は大変です。それでも柔道整復師の資格をとって仕事に活かすためには勉強をしなくてはいけないと理解していれば頑張れます。例えば、自身が将来「最愛の家族の骨折」を治さなければならない時がくるかもしれません。柔道整復師がそのような資格であると分かっていれば、意欲的に勉強に取り組むことができるのではないでしょうか。もし柔道整復師のイメージが明確でない場合は、オープンキャンパスで本校の学生に話を聞いたり、教員に柔道整復師の良いところも大変なところも全部聞いて、なるべくビジョンを明確にしたうえで来ていただけるといいかと思います。
甲斐先生、ありがとうございました!次回のインタビューもお楽しみに!