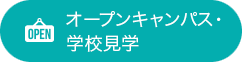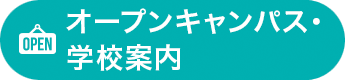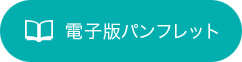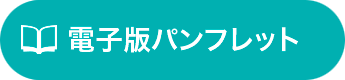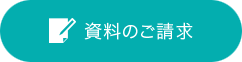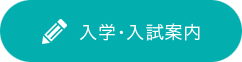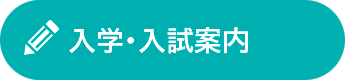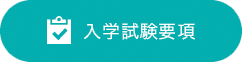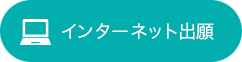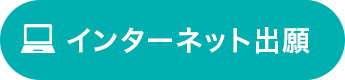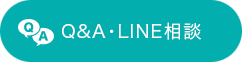【教職員インタビューVol. 12】ライフケア学科 臨床検査専攻 矢嶋望見先生にインタビューしました!
こちらのページでは、教職員がていたんの魅力などをご紹介しています✨
InstagramやXにも学生の日常の様子を掲載しています♪ぜひフォローしてください!
ライフケア学科 臨床検査専攻 矢嶋 望見 先生にインタビューをしました♪
今回のインタビューは、インターン生が取材・作成・投稿を担当しています!

![]()
Q:これまでの経歴を教えてください。
A:学生時代は、血液や尿・便・人間の細胞や寄生虫などヒトの検査をするための材料となっている検体を、病院や学校、企業などから集めて分析する検査センターというところで助手をしていました。
卒業後は病院に就職し、院内での検体検査に加えて心電図検査や採血など患者さんを直接検査する生理学的検査に従事しました。また、健康診断を院内で行うドック・検診センター、企業や学校に行き、そこで検診業務を行う巡回検診、在宅医療にも携わる機会がありました。
新しいクリニックの立ち上げも経験し、医療事務にも従事しました。
教員になる直前では、臨床工学技士として病院の透析室に勤務していました。この様に振り返ると広く浅くにはなってしまいますが、色々な経験をすることができたなと感じます。
![]()
Q:本学の臨床検査コースの特徴・魅力は何ですか?
A:「短い期間で必要な資格を取得する。」を掲げて、学生も教員も頑張っている学校だと思います。早く就職することを目標にしている学生もいますし、専攻科に進学し臨床検査技師と臨床工学技士のダブルライセンスと、学位の取得を目指す学生もいます。短い期間といっても国家試験を受験するための必要単位数は決まっていますから、4年制大学よりもギュッと中身のつまったカリキュラムになってしまうことは否めません。
そんな中、一緒に頑張ってきたクラスメイトは一生の友達になるでしょうし、実際に卒業して臨床検査技師として働いている子たちが訪れてくれるのは教員としてはうれしいですね。
Q:担当する授業について教えてください。
A:患者さんを直接検査する生理機能検査の科目を担当しています。皆さんが聞いたことのあるものと言えば、心電図や脳波、超音波検査などでしょうか。
ほとんどの検査は機械化されていて、臨床検査技師になるにはその機械の使用方法はもちろん、機械の原理、評価方法、他検査に必要な知識を学んでいく必要があります。授業で取り扱う心臓や神経というものは、電気信号によって働いていますが、目に見えるものではないので自分の中でイメージができないと理解することが難しくなります。授業では配付プリントにイラストを使用したり、説明を工夫するなどして、具体的なイメージができるように心がけています。
実習では授業で学んだことを基に、学生同士で実際に検査を行います。生理検査では患者さんと接するので、接遇についても学びます。脱衣で行う検査もありますので、実際に自分も服を脱いで検査を受けることで患者さんの心理状態なども経験し、検査だけではなく総合的に学びを深めていきます。
![]()
Q:帝京短期大学生の印象を教えてください。
A:どの学科も将来への目的意識をもって入学してくる学生がほとんどですので、ふんわりとした雰囲気の1年生が卒業間近になるとしっかりした大人な顔つきになってきます。国家試験があるコースはどこも同じかと思われますが、一生分勉強したと言えるくらい勉強漬けになりますから、ここにきて勉強しなさいと言われる学生はほとんどいません。成長が表情にでてくるんですよね。先生同士で、「あの子成長したね」という話題も多いです。そう考えると伸びしろがたくさんある学生たちなのだと思います。
Q:学生対応で心がけていること・大切にしていることはありますか。
A:教員の中では比較的学生と年齢が近い方なので、話しやすい雰囲気を持てるように心がけています。クラスは少人数で一人一人に目の行き届きやすい環境ですから、学生のことは担任同士で共有していますし、悩みがあるときは小さな悩みのうちに打ち明けてもらえばいいなと思います。
学生一人ひとりに考えや思いがあると思いますので、それを聞いたうえでこちらの伝えたいことを話すという姿勢でいたいですね。厳しく学生に伝えなければならないこともありますが、お互いの考えを共有することで、指導が押し付けにならないように努めています。
![]()
Q:最後に、受験を考えている方へのメッセージをお願いします。
A:臨床検査専攻は卒業後に国家試験を受験して、合格することが目的となりますが、3年間毎日毎日ずっと勉強だけするということは不可能です。特に臨床検査専攻で学ぶ上では、高校の化学・生物の知識が重要ですが、入学後に基礎から学ぶカリキュラムになっていますので、文理は問いません。勉強するときは勉強する、遊ぶときは遊ぶとメリハリをつけて過ごしてもらえたらと思います。そのためには高校生のうちから勉強の習慣をつけること、自分の勉強方法を知ること、この2つを身につければ、大学生活がスムーズに送れると思います。頑張ってください!
矢嶋先生、ありがとうございました!次回のインタビューもお楽しみに!